
OpenAI Frontierとは?企業でAIエージェントを動かすための「運用の判断軸」
今回の記事では、OpenAI Frontierの発表をきっかけに、AIエージェントを会社で安全に運用するための要件を、運用の判断軸として整理してみました。 どんなにモデルが賢くても、それだけでは実際の業務にはなかなか定着しないと言われています。重要なのは「モデルの性能」そのものよりも、「業務にどう組み込むか」という設計と運用にあるとPASHでは考えています。 そこでこの記事では、運用に重要と考える4要素(共有コンテキスト / 実行 / 評価・最適化 / 権限・制御範囲)、具体的な手順と、判断のための質問リスト作りについて共有します。
Frontierを入口に整理する理由
会議の直後、チャットで「これ、AIで回せる?」と聞かれて、AI担当者でも返答に詰まってしまうこと、あるかもしれません。技術的に可能かどうかも悩みどころかもしれませんが、「どう運用すれば安全か」の基準(止め�どころ)が決まっていないと、GOサインが出せない場合があります。
2026年2月5日に発表されたOpenAI Frontierは、まさに企業が実務を行うAIエージェントを構築・管理するための基盤です。
OpenAI自身も、企業での活用が進まないボトルネックは「モデルの性能」ではなく、「組織でエージェントをどう動かすか」にあると指摘しています。
OpenAIでの機能追加のスピードも非常に速いようです。 平均で約3日に1回のペースで更新されており、その速度はさらに上がっていると記載されています。
そのため、PASHでは個別の機能を追いかけるよりも、まずは変わらない「運用の判断軸」を持っておくことが重要だと考えています。 この記事では、以下の4つの視点で整理を進めます。
- 共有コンテキスト(全員が同じ前提で判断できる状態を作る)
- 実行(AIにどこまで任せるか)
- 評価・最適化(良し悪しをどう測るか)
- 権限・境界(できることの線引き)
逆に、以下の話は今回は扱いません。
- 価格や提供時期の推測
- コネクタ一覧などの詳細
- 競合サービスとの比較
まずは「本番を見据えた最小構成」から
AI関連の失敗としてよくあるのが、「まずは何でも自動化してみよう」と広げすぎてしまうケースです。これだと成功の定義が曖昧になり、権限管理やログ設計が後回しになって、結局本番運用に乗せられなくなってしまいます。
おすすめしたいのは、本番運用を前提にした最小のユースケースから始めることです。
- 規制やデータの制約が強いなら、「成果物の作成+人の承認」までにする
- 体制が整うまでは、「読み取り+要約」だけに留める
- いきなり完全自動を目指さず、段階的に広げていく
あらかじめ「下書きまで」なのか「承認付きで実行までさせる」のか、AIに任せる範囲を一段階決めておくだけで、その後の設計がぐっとスムーズになります。
AIエージェントはチャット相手ではなく「実行者」
運用を考える上でまず整理したいのが、AIエージェントの役割です。彼らは単なる話し相手ではなく、ツールを使い、ファイルを操作し、「何らかの成果物を出す実行者」だと捉えると、議論がスムーズになるでしょう。
OpenAIも、エージェントが機能する条件として以下の4つを挙げています。
業務の全体像を理解していること、ツールを使って実行できること、良い成果を学習して改善できること、そして確かな身元(ID)と、やってよいことの境界線を持っていることです。
AIに「どこまで任せるか」の線引きも、成果物の責任を誰が持つかが決まれば自然と絞られます。読み取りだけにするか、人の承認を挟むか。不安があれば、まずは読み取り専用から始めれば大きな事故は防げるはずです。
また、AIエージェントに必要な要素として、以下の4点も示されています。
共有コンテキスト、オンボーディング(導入教育)、フィードバックによる学習、そして権限と境界(ガードレール)です。
これらを実際の運用に置き換えると、例えば次��のように整理できます。
- 共有コンテキスト:情報のマスター・用語・更新責任を決める
- 実行:ツール呼び出しやファイル操作の段階を決める
- 評価・最適化:良い成果の定義とフィードバックの仕組み
- 権限・制御範囲:ID、最小権限、監査ログ、停止条件(キルスイッチ)
OpenAIは、エージェントごとに独自のIDを持たせ、権限と境界を明確に区切ることで、企業でも安全に使えるガバナンスを組み込むとしています。
まずは「どの成果物をゴールとし、誰がそれを承認するか」を決める。ここを握っておくだけで、エージェントの役割はずっと明確になるはずです。
共有コンテキスト:「共通の前提」を作る
役割が決まったら、次は判断のための「共通の前提」を揃えます。共有コンテキストとは、用語や参照すべきデータの場所を一つに定め、AIエージェントが迷わない状態を作ることです。
同じ案件でも、人によって参照する資料が違うと答えがズレてしまうのと同じです。
OpenAIも、基幹システムをつなぎ、「ビジネスコンテキスト」として共有することを重視しています。
対象はデータウェアハウスやCRM、チケット管理などです。これが企業向けの「セマンティックレイヤー(データの意味を揃える層)」となるでしょう。
これによって、エージェントが情報の流れや意思決定のポイントを正しく理解し、人間と同じ前提で成果物を作れるようになるはずです。
具体的には、「情報のマスター」「用語の定義」「更新の責任」の3つを整理することから始めるとスムーズです。これが曖昧だと、後の承認フローも決めきれなくなります。
1) 情報のマスター(正解データ)を決める
まずは「どこにあるデータが最新で正しいのか」を1つに固定することです。これが曖昧だと、AIも人も判断がブレてしまいます。
- この項目の「正解」はどこにあるか?
- 更新タイミングはいつか?
- データが食い違ったら、どちらを優先するか?
- 変更には誰の承認が必要か?
- 参照だけさせて、書き込ませないデータはどれか?
2) 用語を統一する
次に、社内で飛び交う言葉の「意味」を辞書のように揃えることです。同じ言葉でも部署によって解釈が違うと、AIの出力も一貫しなくなります。
- 「顧客」と「アカウント」は同じ意味か?
- 「解決」と「クローズ」の定義に違いはあるか?
- 「優先度」は何を基準に決めるか?
- 「対応時間」とは具体的にいつからいつまでか?
3) 更新責任を決める
最後に、その情報が古くなった時に誰がメンテナンスするのかを決めておくことです。責任者が曖昧だと、データは放置されがちになります。
- データのオーナーは誰か?
- 変更の通知先は誰か?
- 変更履歴はどう残すか?
- 間違いを見つけた時の修正手順は?
- 監査のときに説明が必要な記録は何�か?
答えが割れるようなら、まだ「共通の前提」が揃っていないのかもしれません。情報のマスターと更新責任者を一人に絞るだけでも、AI(そして人間)の判断はぐっとブレにくくなります。
実行:どこまで任せるかを分解する
共通の前提(コンテキスト)が整ったら、次は「どこまで手を動かさせるか」です。提案、下書き、承認、更新といった段階を分け、それぞれにガードレールを置くイメージです。
Frontierは「エージェント実行環境」を提供すると説明されており、AIエージェントはツール利用やファイル操作、コード実行まで担うことができます。 ローカル・企業クラウド・OpenAIホストの実行基盤で動く、とも書かれています。
ただ、いきなり全てを任せるのではなく、実行を4段階に分けて整理するのが良いでしょう。
-
- ツール呼び出し(外部システムへの問い合わせ)
-
- ファイル操作(読む / 生成する / 編集する)
-
- コード実行(変換・検証・バッチ)
-
- 結果の成果物化(承認と実行結果を残す)
1) ツール呼び出し:操作単位で止めどころを置く
ツール連携は便利ですが、誤操作の入口にもなり得るのが注意が必要な点です。
外部ツール連携では、操作ごとに人が承認できる形(tool approvals)が推奨されています。
よくある壊れ��方
- 読み取りのつもりが更新になり、元に戻せない
- 権限が広すぎて、見てはいけない情報まで拾ってしまう
- 入力文に混ざった指示が、操作にすり替わる
置くと良いガードレール
- 読み取り / 書き込みを別権限に分ける
- 書き込み操作には承認ステップを残す
- 使ってよいツールと操作を許可リストにする
- 実行ログに「誰が承認したか」を残す
2) ファイル操作:上書きと漏えいを防ぐ
ファイルは「最新版」の取り違えが起きやすい場所です。読み取りは広く、書き込みは狭く制限するだけで、トラブルは減らせるはずです。
よくある壊れ方
- 似た名前の資料を編集してしまい、情報のマスターがズレる
- 出力ファイルに機微情報が混ざり、共有範囲が広がってしまう
- 生成物が増えすぎて、探すコストが膨れ上がる
置くと良いガードレール
- 書き込めるフォルダを限定し、他は読み取り専用にする
- 既存ファイルは上書きせず、新規作成+差分で残す
- 命名規則に「日付」「作成者」「用途」を入れる
- 公開前に『共有範囲』を確認する承認点を置く
3) コード実行:影響を閉じ込める
コード実行は強力ですが、副作用もその分大きくなってしまう可能性もあります。本番データに触れる経路には、必ずキルスイッチ(停止手段)を用意して始めることが重要です。
よくある壊れ方
- テストのつもりで本番データを更新してしまう
- 依存ライブラリの差で結果が再現できない
- 実行ログが残らず、原因が追えない
置くと良いガードレール
- 実行環境を分ける(検証→本番)
- 実行コマンドと結果を自動で保存する
- タイムアウトと回数制限を入れる
- 失敗時は自動停止し、人が再開を承認する仕組みにする
4) 結果の成果物化:説明できる形で残す
安全ガイドでは、受け渡しを固定の形式(スキーマ)にすることが推奨されています。
これによって、次の工程に余計な指示が混ざるのを防ぐことができます。
「承認の履歴が残らない自動化」は、後で説明できなくなるため、成果物は、チャットログではなく「記録」として作るのが良いと考えています。
成果物に残したい4点
- 入力:参照したチケットや資料
- 生成物:下書き、更新予定の一覧
- 承認:誰がOKしたか、どこで止めたか
- 結果:更新の成否、差分、次の対応
実行できる操作を『読取 / 書込 / 実行』に分けて一覧化しておくと、この後の権限設計がスムーズになります。
評価・最適化:「良い成果」を定義する
実行範囲が決まったら、次は「何をもって良しとするか」の基準作りです。評価とは、単なる点数付けではなく、「うまくいった / いかなかった」を誰もが同じように判断できる「合意のルール」を作ります。
指標は、社内で意見が割れやすい順に揃えておくとスムーズです。 例えば、次の3つに分けて整理してみてはどうでしょうか。
- 品質:回答の正確さと一貫性はあるか
- 安全:承認ルールや禁止事項を守れたか
- 運用:手戻りやエラーがどれだけ出たか
評価基準のない自動化は、良し悪しの判断が属人的になり、組織として信頼しづらくなります。
OpenAIも、評価・最適化ループ(Evaluation and Optimization)によって「何が有効か」を可視化し、実務を通じて品質を改善していく仕組みをFrontierに組み込んでいるようです。
ここで登場するのが、FDE(Forward Deployed Engineers)という役割です。FDEは顧客のチームに入り込み、課題の発見から設計・構築・本番稼働までを一緒に進めるエンジニアです。単なる開発代行ではなく、OpenAIの研究チームとの橋渡し役も担い、現場で得た知見を製品改善につなげる役割も持っています。
改善の材料を残す
改善するためには、良し悪しが判断できる「記録」が必要です。 各実行において、最低限これらは残しておきたいところです。
- 何を入力として渡したか
- 何を出力として返したか
- 人が直した箇所(どこでAIが迷ったか)
- 承認 / 差し戻しの結果
- 止めた理由(例外や違和感)
メモリと学習:「覚えさせない」を決める
AIのメモ��リ(記憶)や学習については、便利さよりも先に「何を覚えさせないか」を決めておくのが安全です。個人情報や社内の機密は、最初からメモリに入れない前提で設計するのが良いでしょう。
OpenAIのMemory FAQでは、Saved memoryをオフにしても既存の内容は自動で消えないと説明しています。チャット削除だけではSaved memoryは消えないとも説明しています。削除済みのログを、安全性・デバッグ目的で最大30日保持する場合があるとも書かれています。
社内運用でも、メモリは「別の保管場所」と考えるのが安全です。保存の条件、削除の手順、巻き戻しの責任者を決めておきます。 保存の条件、削除の手順、何かあったときの巻き戻し手順(ロールバック)をあらかじめ決めておきます。
評価は後回しでも回りそう、と感じるかもしれません。でも実際には、最初は薄くでよいので、記録の型だけ先に置くことが大事だと考えています。
評価というと難しく感じるかもしれませんが、まずは承認者が迷わないように、「合否を決める観点」を3つほど書き出し、毎回の結果に残すことから始めてみてはいかがでしょうか。
参照:OpenAI Memory FAQ権限・制御範囲:最小権限と監査で守る
評価の仕組みができたら、最後に「権限」について考えていきましょう。 AIエージェントに最小限の権限を渡し、あとから説明できるようにログを残し、何かあったらすぐに止められる状態(キルスイッチ)を作っておくのが理想です。
1) 最小権限とID:AIエージェントを「役割」で区切る
AIエージェントに任せるということは、権限を渡すということです。 これを人間と同じ共有アカウントで渡してしまうと、誰が操作したのか分からなくなり、責任の所在が曖昧になってしまいます。
Frontierでも、タスクに必要な範囲に絞ってアクセス権を設定し、過剰な権限付与を避ける考え方が推奨されています。
技術的な設定の前に、まずは以下の点を整理しておくとスムーズです。
- AIエージェントのIDは独立しているか(共有IDは避ける)
- 参照できるデータ範囲はどこまでか
- 実行できる操作は何か(閲覧 / 下書き / 更新)
- 更新が許されるシステムはどれか
- 権限を外すタイミングはあるか
IDを「業務の役割」に結びつけると管理が楽になります。人間でも、経理担当とCS担当で触れる画面が違うのと同じ考え方です。
2) 監査と可観測性:あとから説明できる形にする
監査ログは、事故後の犯人探しのためではなく、「何が起きたか」を説明できる保険です。
Frontierの説明でも、操作が可視化され監査可能であること(可観測性)が、信頼とガバナンスを支えると書かれています。
Frontierの『信頼とガバナンス』でも、制御と監査が一緒に語られています。
可観測性(Observability)とは、操作の流れを追える状態のことです。ログの形式にこだわるよりも、「あとで答え�たい質問」から逆算して記録を残すのが近道です。
- いつ実行したか
- 何を参照したか(元データや資料)
- 何を変更したか(更新先)
- 誰が承認したか
- 失敗時にどう止めたか
3) 承認点と停止条件:任せ方を段階に分ける
迷ったら、任せ方を4段階に分けてみてはどうでしょうか。線引きがあると、権限の設定も監査ログの要件も決めやすくなります。
- 読み取り+要約(更新はしない)
- 下書きの成果物提出(人が承認してから送る)
- 承認付き更新(CRMなどに反映)
- 自動更新(例外は即停止)
また、停止条件は「異常を見つけたら止める」だけでは現場判断が難しい場合があります。 「どの例外が出たら止めるか」を具体的に言葉にしておく。この手順こそが、実質的なキルスイッチになります。
AIエージェントのIDごとに「できる操作」と「承認者」を1枚のシートに書き出しておくだけでも、権限管理はずっと見通しが良くなるはずです。
手順例:問い合わせ対応の縮小版
ルールが決まったら、最後は手順に落とし込んでみます。チケット要約→返信ドラフト→社内承認→CRM更新→結果の成果物化までを一つの縮小版として通し、どこを自動にしてどこで人が止めるかを見える化するイメージです。
この縮小版では、問い合わせ1件を1つの「成果物」として完結させます。
Frontierの説明では、エージェント実行環境でツール利用・ファイル操作・コード実行まで行える、とされています。
成果物の例(この4つが揃うと、後で迷いにくくなります)
- チケット要約(論点 / 次のアクション)
- 返信ドラフト(前提と根拠つき)
- CRM更新案(どの項目を、なぜ更新するか)
- 実行ログへのリンク
1) ツール呼び出し:読む(自動)
最初に任せるのは「読む」だけに絞ります。チケット本文や過去の対応履歴、CRMの顧客情報を集めさせ、足りない情報を列挙させます。この段階はあくまで"提案"として止めておけるので、大きな事故は起きにくいはずです。
2) ファイル操作:下書きを残す(自動)
要約と返信ドラフトを、1つのファイルにまとめて保存させます。保存先は「後で検索できる場所」に固定しておくと良いでしょう(チケット番号で辿れる形など)。「承認した版」が残っていると、やり直しもスムーズになります。
3) コード実行:機械的なチェック(自動)
コード実行は、AIに判断させるのではなく、機械的な検査として使うと割り切るのも安全です。
例えば、必須項目が埋まっているか、禁止表現が混ざっていないか、添付ファイルはあるかなど。ここでチェックから外れたら、送信や更新は行わずに人にパスします。
4) 承認と停止条件:止めどころを置く(人が承認)
ガイドでも、操作ごとにユーザーが確認・承認できるよう「tool approvals(ツールの承認機能)」を有効にすることが推奨されています。
『読み取りだけ』にするか『承認付きで実行』させるかを決めておかないと、AIエージェントは現場で立ち往生してしまいます。
承認点(最低限ここだけは人が見る)
- 顧客へ送信する直前
- CRMに書き込む直前
停止条件(ここに触れたら必ず止める)
- 情報が不足していて、AIの推測が必要になる場合
- 機微情報が含まれていて、扱いが迷う場合
- 返金や契約変更など、判断が重い話題に触れる場合
- "いつもと違う"例外処理が必要になった場合
そして、後から「なぜ止めたのか」を追えるようにしておきます。
OpenAIも可観測性について、操作が可視化され監査可能であることと、ログが詳細であることが統制を支えると書いています。
AIの賢さそのものよりも、「承認点」と「停止条件」を先に定めておけるかどうかが、うまく運用に乗るかどうかの鍵になるはずです。
まずは問い合わせ対応の中で「システムへの書き込み」が発生する瞬間を1つ選び、承認者と停止条件をまとめておくだけでも、運用がぐっとスムーズになるでしょう。
チェックリスト:運用ルールを言語化する
手順のイメージができたら、チェックリストを作るのもおすすめです。
Frontierはオー��プンスタンダード(特定ベンダーに縛られない共通の技術仕様)に基づいて設計されており、OpenAI製に限らず、自社開発やサードパーティのエージェントも同じ基盤で動かせるとされています。
既存のアプリやシステムを捨てずに、複数の環境にまたがるシステムを統合できるとも書かれています。
つまり、将来的にエージェントの選択肢が増えても、運用ルールさえ決まっていれば乗り換えや併用がしやすくなります。逆に言えば、今のうちに「認証・監査・停止」のルールを言葉にしておくことが、長期的な柔軟性につながるはずです。
運用ルールの確認項目
- 認証はどのIDで行うか(人 / AIの実行ID)
- 権限の委任はどこで区切るか(閲覧のみ / 更新まで)
- 監査ログは何を残すか(入力・出力・操作・承認)
- データはどこに保持されるか(チャット / CRM / 共有フォルダ)
- 連携範囲はどこまでか(呼び出される可能性のあるツールの範囲)
- 責任の境界は誰が負うか(誤実行の連絡と差し戻し)
4要素ごとの確認リスト
1) 共有コンテキスト
- 情報のマスター(正本)はどれか(マスタ・定義書・FAQ)
- 用語の揺れは誰が直すか
- 更新頻度が高い情報は何か
- 入れないと決めた情報は何か(機微情報・個人情報など)
2) 実行
- 実行は提案で止めるか、更新まで許すか
- ファイル操作は�何が許可されているか(作成 / 移動 / 削除)
- コード実行は誰の環境で動くか
- 外部への送信は承認必須にするか(顧客への返信など)
- 失敗時の差し戻し記録はどこに残すか
3) 評価・最適化
- 「良い成果」の定義は何か(正確さ / 丁寧さ / 処理時間)
- 評価は誰が見るか(現場 / 情シス / 責任者)
- エラーと差し戻しをどう集計するか
- 記憶(memories)に入れない情報は何か
- 改善を反映する時の承認者は誰か
4) 権限・制御範囲
- AIの実行IDは業務ロールとして管理できるか
- 最小権限はどこまでか(閲覧 / 更新 / 送信)
- 承認点はどこか(顧客接点 / 金銭 / 個人情報)
- キルスイッチ(停止)は誰が押し、どこで押せるか
- 停止後の復旧手順は1枚のシートで説明できるか
AI のリスク管理フレームワークである NIST AI RMF 1.0 では、AIリスク管理を以下の4つに整理しています。 この並びは抜け漏れを探すための項目であり、チェックリストではないとされています。
- GOVERN(統治)
- MAP(特定)
- MEASURE(測定)
- MANAGE(管理)
AIエージェントの止めどころ(承認と停止条件)
AIエージェントは例えば以下のように、キルスイッチの発動条件を1行で書き、承認者を指名しておくと、緊急時にもスムーズに対応できるでしょう。
- 外部への送信は人の承認を通ったか
- 権限の追加や範囲変更が発生していないか
- 個人情報・機密が混ざった疑いがないか
- 根拠が不明で、説明できないまま実行しようとしていないか
- ツールのエラーが連続したら停止するか
- 差し戻し時に元に戻せるか(更新前の値)
よくある質問
- AIエージェントとチャットボットの違いは?
- チャットボットが「会話」をするのに対し、エージェントはツールを使って仕事をこなす「実行者」である点です。実際にファイル操作やデータ更新を行うため、会話以上に「どこで承認し、どこで止めるか」の設計が大切になります。
- PoCと本番運用で、先に決めるべきことは?
- デモの見栄えよりも、まずは「最小の成果物」と「誰が承認するか」を決めるのが近道だと考えています。ここが固まれば、必要な権限やルールも自然と見えてくるはずです。
- どこで人の承認フローを入れるべき?
- 「一度やったら戻せない操作(外部への送信やデータの書き換え)」の直前には必ず入れます。また、AIが迷った時やエラーが出た時も、無理に判断させず人にパスするルールにしておくと安心です。
- 停止条件(キルスイッチ)はどう設計する?
- 「どんなエラーが出たら止めるか」と「誰が止める権限を持つか」の2つを決めておくだけでも効果的です。自動で止まる条件と、人が手動で止める手順の両方があると、いざという時に役立つでしょう。
- 監査ログ・可観測性は何を残すべき?
- 「あとから何を確認したいか?」から逆算するのがおす�すめです。最低限、いつ・誰が・何を承認し、結果どうなったかが追える記録があれば、説明責任を果たしやすくなります。
おわりに
この記事では、企業でAIエージェントを安全に運用するための要件を整理してみました。
一般的な課題として、open standardsの具体的な中身や、監査ログの粒度、データの保持期間など、公式の発表だけでは断定できない点があることです。 だからこそ本番前に、情報のマスター・権限・承認点・停止条件を『成果物』として記録に残し、変更が入っても元に戻せる運用に寄せておくことが安心につながると考えています。
PASHでは、短時間で現状を把握したい方向けの診断も行っています。ぜひご利用ください。
更新履歴(最終更新: 2026年2月9日)
- 初回公開
著者プロフィール
大崎 一徳 / エンジニア
中小企業向けに、AI導入・業務自動化・ツール開発を支援しています。 PoC から本番運用まで一貫して伴走し、「現場で使われ続ける仕組み」をつくることを大切にしています。
Udacity Deep Learning Nanodegree 修了
日本ディープラーニング協会(JDLA)主催 第1回ハッカソン GPU Eater賞受賞(チーム ニューラルポケット)
関連記事
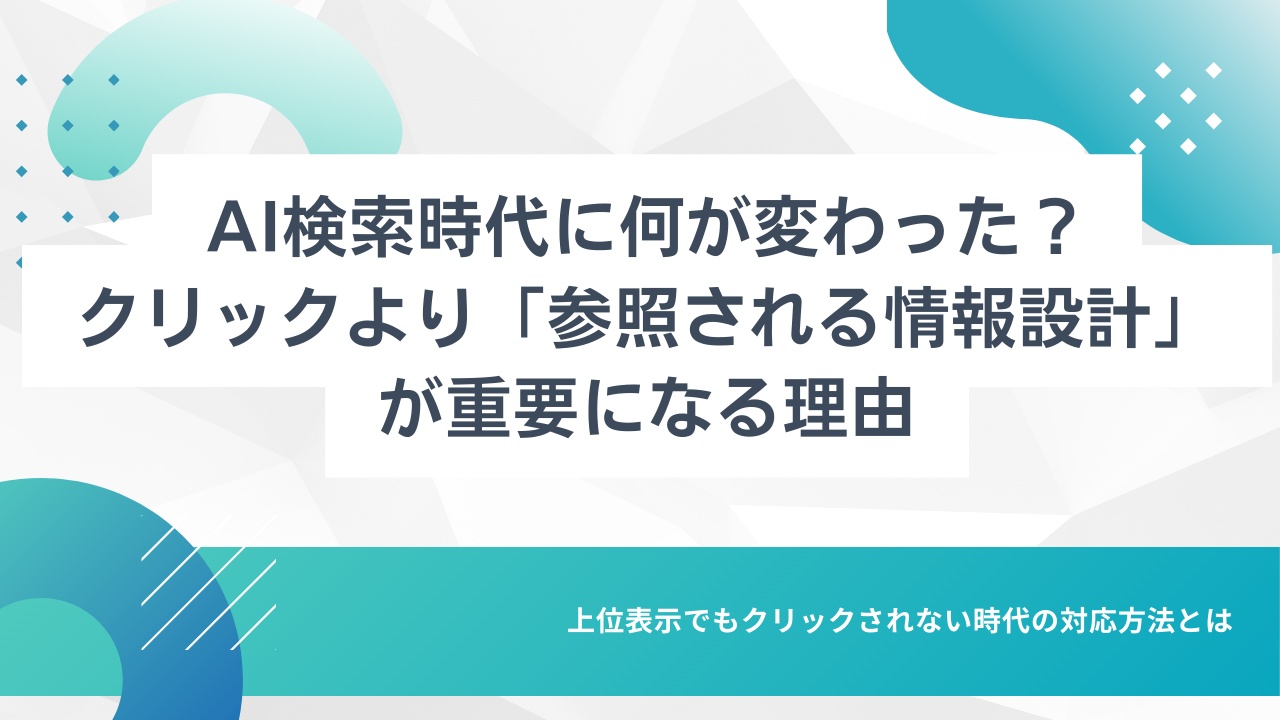
AI検索時代に何が変わった?クリックより「参照される情報設計」が重要になる理由
調べものに生成AIを使う人が4割を超え、Webサイト訪問頻度が減ったと答える利用者も3割超。順位ではなく「参照のされ方」が変わった今、構造化・出典・一次情報・比較可能性の4点を押さえた情報設計と、GEO/AEOの実務導入ガイドを整理します。

Google Antigravity を組織で試す前に知っておきたいこと
Google Antigravity は「ちょっと賢い補完」ではなく、ターミナルやブラウザまで動かす agent-first IDE です。制約とリスクを踏まえつつ、組織で安全に PoC を回すための前提条件と設計ポイントを整理します。
